「小サナル早附木売ノ娘」。デンマークの作家アンデルセンの「マッチ売りの少女」が、明治期に翻訳された時の題だという。古くから日本にもなじみ深いアンデルセンの生誕200年の記念展が、東京?大手町の逓信総合博物館で25日まで開かれている。
アンデルセンは、英国の作家ディケンズと交流があった。英国への招待を受けて送った手紙の複製がある。「私は今、あなたのところに向かって旅をしています……私はロンドンが好きではありませんし、2、3日以上は決してそこに留まらないでしょう……田舎の空気に触れたいと思います」
筆まめだったというが、母親あての手紙は長くみつかっていなかった。最近、デンマーク王立図書館の研究員が発見した。記念展には、その複製も展示されている。「いつもと同じようなおたよりをいたします……最近の旅行記がやっと書き終わりました……お母さんはお元気ですか?……おたよりを楽しみにしています。僕は元気ですよ あなたのクリスチャンより」
これまで、アンデルセンの母親への感情は冷え切ったものといわれてきた。この26歳の時の手紙からは、母親を気遣う新しい一面がうかがえる。
銀座の通りに出ると、救世軍の社会鍋が出ていた。クリスマスの歌が流れ、電飾をまとったツリーが並んでいる。
ディケンズは「クリスマス?キャロル」を著し、アンデルセンは、大みそかの夜の「マッチ売りの少女」を書いた。19世紀の歳末をそれぞれに描いたふたりの会話を想像しながら、人の波に分け入った。
周三 28 12月 2005
12月22日
Posted by yanmin under 天声人语
No Comments
周日 25 12月 2005
12月24日:汪道涵
Posted by yanmin under 讣闻
No Comments
中新上海网十二月二十四日电 海峡两岸关系协会会长汪道涵今天上午七时许在上海逝世,享年九十岁。消息传出,两岸各界人士纷纷扼腕。
汪道涵,生于一九一五年,安徽省嘉山县人,毕业于上海交通大学。一九四九年十月起,历任浙江省财政厅厅长、商业厅厅长、华东军政委员会工业部部长等职,后调往北京任职。一九八一年四月,汪道涵出任上海市市长。
上世纪八十年代中期,汪道涵退居二线后,长期关注海峡两岸和平统一大业。一九九一年十二月,海峡两岸关系协会在北京成立,汪道涵出任会长。
周三 21 12月 2005
12月19日 关鹤岩
Posted by yanmin under 讣闻
No Comments
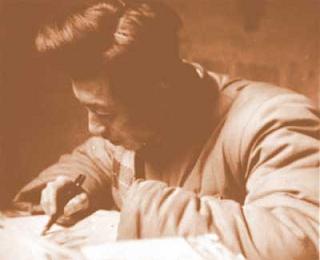 ?????????????
????????????? 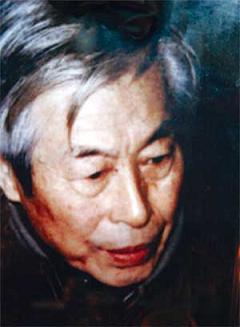
“19日中午12时10分左右,关鹤岩在正午时分离开人世,病房外,应该有暖暖的阳光,像他创作的那首曾温暖了无数人心灵的《丢手绢》,他的人格,他的心灵,永远阳光灿烂”—肖云儒
?
摘自:新浪网
?
周二 20 12月 2005
12月20日
Posted by yanmin under 天声人语
No Comments
0歳から100余歳まで、1年ごとの年齢のもつ意味合いを、各界の著名人がその年でしたことと並べてつづる。英国の動物行動学者デズモンド?モリスの『年齢の本』(平凡社)は、ユニークな視点で描かれた一冊だ。
「15歳は門出の年だ。青年期の若者が成人期にまさに入ろうとする時期であり、刺激的な世界に胸をときめかす」。ビリー?ホリデイがニューヨークで歌い始めた年とある。日本なら、プロ棋士?羽生善治の誕生を挙げるところか。
モリスは、日本を含む多くの国々が、この年齢を義務教育の修了年限にしていることにも触れている。日本の場合は、進学や就職といった試練に直面するこの年を「15の春」と形容してきた。
この人の「15の春」はどうなるのか。フィギュアスケートのグランプリファイナルで優勝した浅田真央さんの見事な演技の映像を見ていて、そんなことを思った。
今年の7月1日の前日までに15歳に達しているのが、トリノ五輪の出場資格の規定だった。浅田さんが15歳になったのは9月だった。この年齢制限の規定は一貫しておらず、その時々で変わってきた。
年端も行かない小学生のような幼子に、才能があるからといって練習や演技を強要しているのなら、より強い規制も必要だろう。しかし今回は「門出の年」に達した人の出場資格だ。伸び盛りの若い人には、独特の胸のすくような勢いがある。重力のくびきを離れる瞬間の姿が五輪で見られないのは残念だ。今の線引きの仕方がくびきになっていないかどうか、再考する価値はある。
周二 20 12月 2005
12月18日
Posted by yanmin under 天声人语
No Comments
「今年はケヤキが不気味な枯れ方をしています」と東京近郊の読者からお便りをいただいた。「葉が縮れたまま散らない」とある。家のそばのケヤキ並木を観察してみた。くすんだ茶色の葉が枝先で絡まり合い、素人目にも様子がおかしい。
ケヤキの巨樹がある立川市の国営昭和記念公園を訪ねた。樹木医の川原淳さんによると、専門家の間でも話題になり始めたところだという。異変に気づいたのは春先で、花が例年になく多く咲いた。夏には緑の葉が茶色に変わり、秋には縮み出した。「病気ですか」と心配する来園者もいた。
関東地方だけではない。京都府立植物園でも今年はケヤキの葉がよじれ、枯れが目立った。名古屋市の東山植物園では、カエデやモミジは例年通りだったのに、ケヤキだけ十分に色づかないまま秋を終えた。山陰や九州でも同様の例が見られた。
「ケヤキの葉が枯れたまま落ちない現象は十数年前からあるが、今年は特にひどい」。植物の生態に詳しい国立科学博物館の萩原信介さんは話す。病虫害ではないようだが、葉と枝を切り離す離層という部位が十分に育たず、北風に吹かれても古い葉が枝から落ちない。
ケヤキは古名を槻(ツキ)と言う。万葉集にも歌われ、戦国時代にはお城の造営に使われた。現代では公園や街路でおなじみで、「けやき通り」や「けやき平」はあちこちにある。
地球温暖化のせいかどうか原因はまだ不明だ。米国の思惑もあって人類共通の温暖化対策がうまく進まない。しびれを切らしたケヤキが身を挺(てい)して何か警告しているのだろうか。
周二 20 12月 2005
12月19日
Posted by yanmin under 天声人语
No Comments
毎年クリスマスが近づくころに読み返したくなる本がある。ドイツの作家ケストナーの『飛ぶ教室』だ。寄宿学校を舞台に一群の生徒たちと、彼らを取り巻く人々との交流の物語である。
主人公の一人は、貧しい給費生のマルチン。冬の休暇直前に故郷から手紙が届いた。父親が失職し、旅費が工面できないという。他の生徒が帰省する中、学校に居残る彼を舎監のベク先生が見つけた。「どうしたわけなのだ」「いいたくありません」
泣き崩れるマルチンに先生は20マルクを渡す。「クリスマスの前日に贈る旅費は返すにはおよばない。そのほうが気もちがいいよ」(高橋健二訳)。その晩遅く、息子の帰還に驚く両親にマルチンがまっ先に言ったのは、「帰りの汽車賃もぼく持ってるよ」だった。
何度読んでも、ここで目頭が熱くなる。本が書かれた1933年は、ヒトラーが政権を取った年だ。世界が不況に沈み、多くの人にとって、貧困や失業は生々しい問題だった。
今からみれば、主人公の抱える友情やライバル関係の悩みは甘っちょろいかもしれない。最近ドイツで映画化された「飛ぶ教室」では、学校への不適応や両親の離婚など現代の状況を織り込み、大胆に改作していた。
しかし、原作の伝えるメッセージに変わりはない。ケストナーは言う。「どうして大人は子どものころを忘れることができるのでしょう。子どもの涙は、決して大人の涙より小さいものではありません」。子どもを暴力や欲望の対象としか見ない悲劇が続く年の終わりに、改めてこの名作を読もうと思う。
周二 20 12月 2005
12月15日
Posted by yanmin under 天声人语
No Comments
アドリア海に注ぐイタリアのルビコン川は、古代ローマ時代にカエサルが「賽(さい)は投げられた」と言って渡った故事で知られる。河口近くの町で見たルビコン川は、幅十数メートルの小さな流れだった。
橋のたもとにカエサルの像が立っている。渡れば元老院に背くことになるその一線を、彼は越えた。川は小さかったかもしれないが、歴史への刻印は大きかった。
耐震強度を偽装した姉歯秀次元建築士が、一線を越えて法に背いたのは、1998年ごろだったという。昨日、国会の証人喚問で証言した。鉄筋を減らすのはこれ以上は無理だと、木村建設側に何度も言ったという。それでも「減らしてくれ」と言われる。「断ると収入が限りなくゼロになる」。そして、ついに「やってはいけないと思いながらやった」
木村建設側は偽装への関与を否定した。真相はまだ分からない。しかし、一線を越えた後、建設され続けた偽装の疑いのある建物は、数十棟にも及ぶという。その一つ一つで営まれていた人々の暮らしが大きくゆさぶられた。捜査による早期の解明を待ちたい。
20年近く前、出張先のローマで、高層住宅の一角が突然崩れ落ちたという現場を見た。別の建物では、ひさしが崩れてけが人が出ていた。その一方、2千年も前のカエサルの時代の建築は往時の姿をとどめている。「永遠の都」の皮肉な一面だった。
国会で、今後の改善策を問われた元建築士は、民間の検査機関の審査を厳しくチェックしてほしいと述べた。偽装建築士が、偽装対策を語る。皮肉な問答だった。
周二 20 12月 2005
12月16日
Posted by yanmin under 天声人语
No Comments
「郵刺客者(ゆうしかくしゃ)」「セパ琢磨(たくま)」「大株主命(おおかぶぬしのみこと)」。住友生命が募集した今年の出来事や気分を表す「創作四字熟語」だ。
こんな作品もある。住宅や駅にサソリやヘビが出没した「行方悲鳴(ゆくえひめい)」。少子化の傾向が止まらない「減子次代(げんしじだい)」。クールビズが広まった「薄衣多売(はくいたばい)」。世界の各地で大きな地震や災害が起きて、「津々揺々(つつゆらゆら)」。大方は、11月までの動きにちなむものだ。そこで主に直近のニュースに即して、及ばずながら思案してみた。
ブッシュ米大統領が演説して、イラクの大量破壊兵器についての機密情報が間違っていたと認めつつ、戦争を正当化した。イラク人の死者は、民間人だけで約3万人ともいう。謝罪とざんげがないのでは、「先制薮主(せんせいぶっしゅ)」の強弁と言われても仕方がないのではないか。
その大統領による先制攻撃をいちはやく支持した小泉首相の責任も、改めて問われる。大統領の開戦責任と、つながっているからだ。大事な日米関係が、「ブ唱小随(しょうこずい)」でいいはずがない。イラクへの自衛隊派遣の1年延長も「米意和達(べいいわたつ)」のように、あっけなく決まった。
国内では、耐震偽装の問題が深刻だ。鉄筋を不当に減らされた「中空楼閣(ちゅうくうろうかく)」が幾つも建てられた。株を巡っての騒動も相次いだ。買い占めに走る「株主総買(かぶぬしそうかい)」があり、誤って発注された株を大量に手に入れたものの、利益を取るかどうか対処に迷う「握銭苦悩(あくせんくのう)」と「取捨忖度(しゅしゃそんたく)」があった。
この一年、殺伐としたニュースが目立った。最後ぐらいは、明るい出来事に期待したい。除夜の鐘までには、まだ少しだが間がある。
周二 20 12月 2005
12月17日
Posted by yanmin under 天声人语
No Comments
アインシュタインは、1922年、大正11年の暮れの今頃、京都、奈良を夫婦で旅していた。ノーベル物理学賞の受賞が決まったばかりで、東京や仙台、名古屋などでも盛んな歓迎を受けた。東京では小石川植物園で帝国学士院の歓迎会があり、記念写真が残された。
戦後の昭和39年、その植物園に英国からリンゴの苗木がやってきた。ニュートンが万有引力を発見したとの逸話のあるリンゴから接ぎ木されたものだった。その時、科学の巨人ふたりの接点が小石川にできた。
「ふたりのどちらが、科学や人類により貢献したか」。アインシュタインの特殊相対性理論などの発表から100周年の今年、英王立協会が投票を募った。
「科学への貢献」では、協会の科学者も一般人も、ニュートンの方がかなり多かった。「人類への貢献」では、科学者の6割がニュートンだが、一般人では、票は半々に分かれた。
2000年に、本紙が、この千年の傑出した「日本の科学者」を読者から募集した。「日本の」なのに、科学に国境はないというのか、外国人を挙げる人もいた。そのトップはアインシュタインで、ニュートンは5番目だった。
アインシュタインは、自宅の書斎にニュートンの肖像を飾っていたという。「ニュートンにとって自然は一冊の開かれた書物であり、その文字を難なく読むことができた」とも述べた(金子務『アインシュタイン劇場』青土社)。昨日、冬空に枝を差し伸べる小石川のリンゴの前で、自然という書物を前人未到の目で読み解いたふたりのことを考えた。